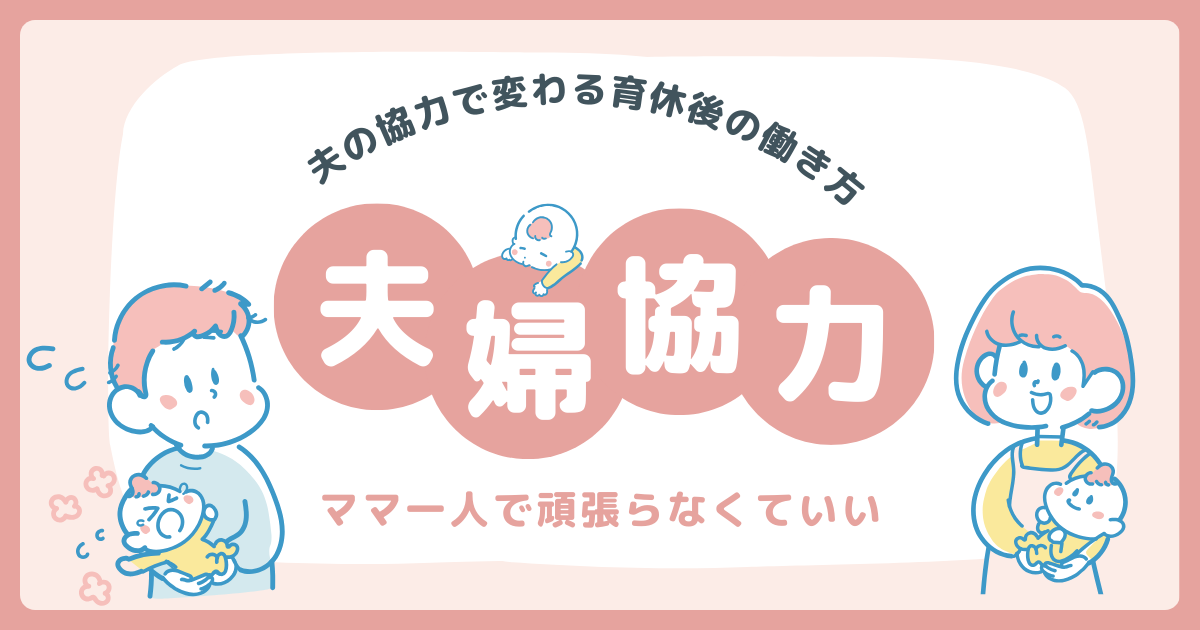育休後に職場へ復帰しても、その後の働きやすさは「家庭でどれだけ協力を得られるか」に大きく左右されます。朝の準備、保育園への送り迎え、子どもの急な発熱…。
一つひとつは小さな出来事でも、積み重なるとママ一人では抱えきれないほどの負担になります。
とはいえ、夫の協力は家庭によって大きな差があります。
「家事も育児も積極的に担ってくれる夫」もいれば、「手伝っているつもりでも妻から見るとまだ足りない」というケースも少なくありません。
協力が得られずワンオペ状態になってしまうと、せっかく復職しても続けることが難しくなる現実があります。
私自身、専業主婦だった母から「育児で男の人の仕事を邪魔するんじゃない」と言われて育ちました。
その影響で「子育ては女性が背負うもの」とどこかで思い込み、実際に私も一人で抱え込むことが多かったのです。
正直に言えば「ワンオペがつらい」という声に共感しにくい部分もありました。
けれど今の時代は、ママが一人で背負い続けるのではなく、夫婦や家族が“チーム”として子育てに向き合うことが求められています。
この記事では、育休後に夫の協力がどのくらい必要なのか、そして協力が得られにくいときにどう工夫できるのかを考えていきます。
育休後に直面する家事・育児の現実
育休後に職場へ戻ると、多くのママが最初にぶつかる壁は「家庭の時間が圧倒的に足りない」という現実です。
朝は子どもを起こし、ごはんを食べさせ、着替えさせ、保育園へ送り出すまでが一仕事。
仕事から帰れば、迎えに行き、夕食の支度、お風呂、寝かしつけまでノンストップで動き続けることになります。
さらに小さな子どもは体調を崩しやすく、発熱や呼び出しで予定が急に崩れることもしばしばです。
職場での責任と家庭での突発的な対応、その両方を同時に背負うことは、想像以上に大きな負担となります。
こうした日々の積み重ねは、体力的な疲れだけでなく「自分ばかりが頑張っている」という心理的な重さにもつながります。
特に家庭内での分担が偏っていると、復職を続ける意欲そのものを揺さぶる要因になりかねません。
だからこそ、育休後を無理なく乗り越えるには、家庭内の協力体制をどう整えるかが重要です。
仕事の制度や職場環境だけでなく、家庭という足場が安定しているかどうかが、働き続けられるかどうかを大きく左右するのです。
育休後に夫の協力はどのくらいあるのか
育休後に働き続ける上で、夫の協力がどの程度あるかは大きな分かれ道になります。
けれど現実には、「思っていたより協力が少ない」と感じるママは少なくありません。
たとえば、内閣府の調査では、日本の男性が家事・育児にかける時間は一日平均で2時間弱。
これは欧米諸国と比べると半分以下というデータもあります。夫の側からすると「仕事で疲れている中でも手伝っている」という感覚がある一方で、妻から見ると「生活全体の流れを支えるにはまだ足りない」と感じられる。
この“意識のギャップ”が、育休後の家庭でよく起こるすれ違いです。
また、協力の内容にも差があります。
保育園の送迎や病児対応など、勤務に直結する部分をどこまで夫が担えるかは、ママの働き方の自由度に直結します。
送り迎えを毎日任せられなくても、「週に数回は担当する」「急な呼び出しは交代で対応する」など、小さな分担でも大きな支えになるのです。
逆に夫の協力が得られにくい場合、ママは「結局すべて自分がやらなければならない」というプレッシャーを抱えがちになります。
復職を継続できるかどうかは、仕事の制度や職場環境だけでなく、この“夫の協力度合い”が左右しているといっても過言ではありません。
育休後も私がワンオペを当たり前と思っていた理由
私自身、育休後に復職しても「夫に協力を求める」という発想があまりありませんでした。
というのも、専業主婦だった母から「育児で男の人の仕事を邪魔するんじゃないよ」とよく言われていたからです。
父は仕事に集中し、母は家事と育児をすべて担う。
それが“当たり前”という価値観の中で育った私は、結婚後も無意識に「子育ては自分が背負うもの」と思い込んでいました。
その結果、夫が協力してくれなくても「仕方ない」と受け止め、自分一人で抱え込むことが普通になっていました。
正直に言えば、「ワンオペで辛い」という声を耳にしても「それでも頑張るしかないのでは?」と考えてしまうところがあったのです。
しかし、実際に復職してみると、仕事と家庭の両立は想像以上に過酷でした。
仕事で成果を求められながら、家庭では小さな子どもに24時間体制で寄り添う。
母の時代は「夫が働き、妻が育児を担う」ことが当然とされていましたが、今は女性も仕事を続けることが一般的になっています。
その中で「妻が一人で背負う」やり方を続けるのは、現実的ではなくなっているのだと痛感しました。
この経験から、「協力を求めることは甘えではない」「夫婦で分担するのは時代に合った選択」だと考えるようになったのです。
育休後を続けるために夫婦で分担を見直す方法
育休後に無理なく働き続けるためには、家庭の中で「どこをどう分担するか」を具体的に見直すことが欠かせません。
夫婦で話し合いをしないままなんとなく役割が固定されてしまうと、ママに負担が集中し、心身ともに限界を迎えてしまうこともあります。
まず大切なのは、朝と夜の時間帯で役割を分けることです。たとえば、朝の送りは夫、夜の寝かしつけは妻といったように、時間軸で分けるとお互いの生活リズムに合わせやすくなります。
次に重要なのが、子どもの体調不良時の対応をどうするかを事前に決めておくこと。
呼び出しが来るたびに「今日どちらが行くのか」で揉めてしまうと、それだけでストレスが増します。週ごとに交代する、重要な会議の日だけはあらかじめ伝えておく、など家庭に合ったルールを作ると安心です。
また、家事については「夫婦で全部分け合う」ことだけが正解ではありません。
外部サービスや家電を積極的に活用するのも大きな助けになります。宅配食材、食洗機、乾燥機付き洗濯機などを導入するだけで、日々の負担がぐっと軽くなります。
そして何より大切なのは、「手伝う」ではなく「担う」意識を共有することです。
夫が「手伝ってあげている」という感覚のままでは、どうしても妻に主導権と責任が偏ってしまいます。
育児や家事は本来、夫婦が一緒に担うもの。お互いに「この家庭を一緒に回している」という意識を持つことが、育休後の生活を支える大きな力になります。
育休後に夫の協力が難しい場合の選択肢
理想は夫婦で分担することですが、現実には「夫の仕事が多忙で協力が難しい」「単身赴任で不在が多い」といったケースも少なくありません。
その場合でも、ママが一人で抱え込まずにすむ方法を考えておくことが大切です。
まず活用したいのは、実家や親のサポートです。
送り迎えや病児対応など、限定的でも助けてもらえるだけで大きな安心につながります。
頼ることに抵抗を感じる人もいますが、短期間でも支えがあると復職の継続性は格段に高まります。
次に選択肢となるのが、ファミリーサポートやベビーシッターといった外部サービスです。
費用はかかりますが、いざという時に「頼れる先がある」と思えることは精神的な余裕を生みます。
自治体によっては補助制度がある場合もあるので、事前に調べておくと安心です。
また、職場の制度を柔軟に使うことも有効です。
時短勤務や看護休暇を必要に応じて組み合わせることで、すべてを一人で背負い込まずに済みます。
大切なのは「夫が無理だから自分が全部やる」のではなく、利用できる制度やサービスを広く見渡しながら選んでいく姿勢です。
「私が頑張らなければ」という思いは、多くのママが抱えるものです。
しかし、その頑張りが続かなくなってしまっては本末転倒。
夫の協力が難しいときこそ、家庭の外に視野を広げて支えを得ることが、育休後を乗り切るための現実的な解決策になるのです。
まとめ|育休後は家庭を“チーム”にして乗り切る
育休後の働き方を続けられるかどうかは、制度や職場環境だけでなく、家庭のサポート体制に大きく左右されます。
特に夫の協力は、ママの負担を軽くし、心の余裕を生み出す大切な要素です。
私自身は「子育ては女性が背負うもの」という母の価値観を引き継ぎ、ワンオペを当たり前だと思っていました。
しかし実際に復職してみると、仕事と家庭の両立は一人で背負うにはあまりにも重すぎることを痛感しました。
今の時代、夫婦がともに育児を担うのは特別なことではなく、むしろ自然な形なのだと感じています。
もちろん、夫の協力が得られにくいケースもあります。
そんなときは、実家や外部サービス、制度を組み合わせることで「家庭をチームにする」工夫ができます。
大切なのは「私だけが頑張る」状態をつくらないこと。
辛さを声に出すことは弱さではなく、より良い仕組みを築くための第一歩です。
育休後を一人で戦うのではなく、家庭全体をチームとして整えていくこと。
それこそが、無理なく働き続けるための一番の近道なのです。