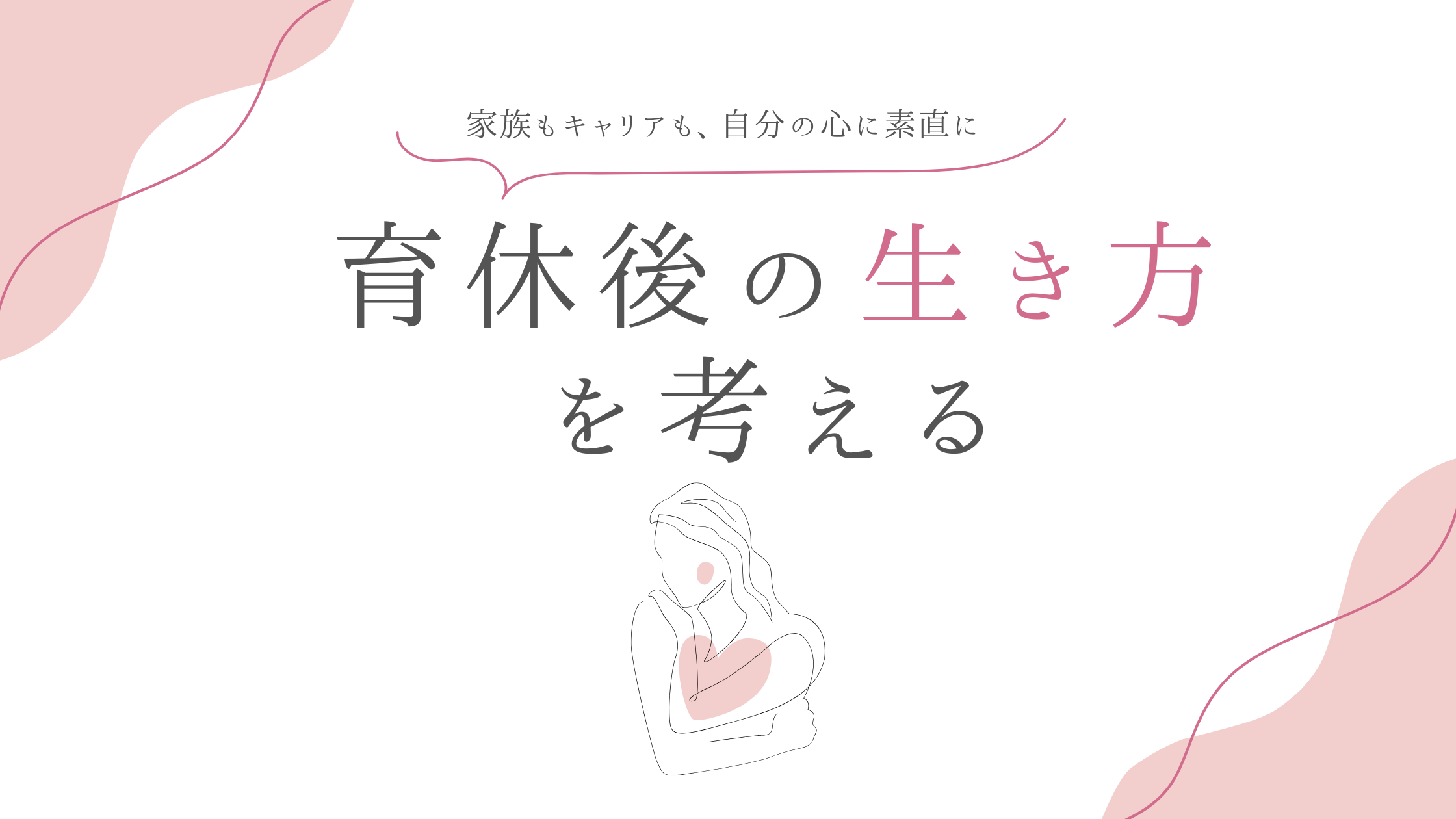保育園入園前、あるいは入園が決まったばかりの時期。
ワーママにとって、このタイミングの仕事選びは、ただ「働く場所を見つける」以上の意味を持ちます。
なぜなら、この時期に選んだ働き方は、その後数年間の生活リズムや家族の形を大きく左右し、キャリアの方向性までも決めてしまう可能性があるからです。
朝の送り迎えに始まり、急な発熱や行事参加、帰宅後に待ち構える家事の山……。
頭では「仕事と家庭の両立が大事」とわかっていても、現実は体力・時間・心の余裕が削られやすく、理想通りにはいかないことも多いでしょう。
だからこそ、「どこで働くか」より先に、「私はどんな人生を送りたいのか」という根本的な問いに向き合う必要があります。
キャリアを続けたいのか、家事育児を優先したいのか、それともその両立を目指すのか??。正解はありません。けれど、自分で選んだ答えこそが、これからの毎日を支える軸になるのです。
育休後、まずはどのように生きたいかを明確にする
育休後の働き方を考えるとき、最初に取り組むべきは「職場復帰の準備」ではありません。
まずは、自分自身に問いかけることです——これから、どのように生きたいのか、を。
キャリアを優先して働くのか、家事や育児を軸に生活を組み立てるのか、それともその中間を目指すのか。
この選択は、単なる働き方のスタイル決めではなく、これから先の数年間の生活全体の形を左右します。
キャリアを残したい場合、スキルの維持や昇進の可能性を追うことができ、将来的な収入や自己実現にもつながります。
しかし、そのためには家族や外部のサポート体制が不可欠で、時には自分一人の頑張りだけでは成り立たない場面もあります。
一方、家事や育児を優先する働き方は、子どもとの時間をしっかり確保でき、家庭に余裕を持たせやすいのが魅力です。
ただし、収入減や社会的接点の減少といった現実的な課題も伴います。
両立型を目指す道もありますが、その場合は勤務時間、通勤距離、職場の柔軟性など、条件がそろって初めて可能になります。
条件が不十分なまま両立を目指すと、心身の負担が増し、結局どちらも中途半端になってしまうこともあります。
育休後のスタートラインに立つときは、周囲の意見や世間の「理想像」に振り回されやすくなります。
だからこそ、自分が本当に大切にしたいことを紙に書き出す、家族と率直に話すなど、自分の軸を見える化しておくことが大切です。
この「どう生きたいか」という土台が決まれば、職場復帰か転職か、在宅か通勤か、といった細かい選択もブレなくなります。
育休後もキャリアを残す働き方を選ぶ場合のポイント
育休後もキャリアを継続していく道を選ぶ場合、最初に考えるべきは「自分一人で背負いすぎない仕組み」を作ることです。
出産前と同じように仕事をこなすのは、家庭と育児の負担が増えた状態では現実的ではありません。持続可能な働き方にするためには、意識的に負担を分散させる必要があります。
1. 協力体制を整える
キャリアを残すためには、配偶者や家族のサポートが不可欠です。
送り迎えの分担、家事の役割分担、休日の子どもの世話など、具体的に「誰が・いつ・何をするか」を明確に決めておきましょう。
また、実家や親戚が近くにいない場合は、地域のサポート制度(ファミリーサポート、自治体の一時預かりなど)を事前に調べて登録しておくと安心です。
2. 外部サービスを賢く使う
キャリア維持のために、家事や育児の一部を外部に委託するのは立派な選択です。
- 家事代行サービス(掃除・洗濯・料理)
- 病児保育やベビーシッター
- 宅配ミールキットやネットスーパー
これらは費用がかかりますが、その分生まれた時間を仕事や休息に回すことで、長期的なパフォーマンス維持につながります。
3. 無理をしない仕組みをつくる
復職直後は、業務量や責任範囲を以前と同じレベルに戻すのではなく、段階的に増やすのが理想です。
必要であれば時短勤務やリモート勤務を活用し、自分と家族の生活リズムに合わせて調整しましょう。
しかし実際には「時短勤務のはずなのに、業務量が多すぎて時短になっていない」というケースも少なくありません。そんなときは、我慢を続けるよりも、部署異動や業務調整を上司に相談するのも一つの手段です。
「頑張ればなんとかなる」という発想は、一時的には成立しても、長期的には体調やメンタルに影響します。
4. キャリアの方向性を定期的に見直す
育休後は、子どもの成長や家庭の事情に合わせて働き方を変える必要が出てきます。
年に1回でも、自分のキャリアの方向性と現状を見直す時間を取り、「このままで良いか」「何を変えるべきか」を判断しましょう。
キャリアを守るための働き方は、「自分だけの努力」ではなく「協力体制」と「環境づくり」で成り立ちます。
この土台があれば、育休後も無理なくスキルと経験を積み上げていけるのです。
育休後は家事・育児を優先する働き方を選ぶ場合のポイント
育休後、「今はキャリアよりも家庭を優先したい」と考えるのも立派な選択です。
特に保育園期は、子どもの成長を間近で見守れる貴重な時期。
仕事に多くの時間を割くより、家庭の時間を優先することで得られる満足感や安心感は大きなものです。
ただし、その働き方が成り立つためには、収入・時間・精神面のバランスをしっかり整える必要があります。
1. 家計のシミュレーションを行う
家庭優先の働き方にすると、多くの場合収入が減ります。
その減少分が生活にどの程度影響するのか、家計簿やシミュレーションアプリを使って試算しましょう。
教育費や将来の貯蓄目標も考慮に入れると、安心して働き方を選べます。
2. 働き方のバリエーションを検討する
家庭優先でも、収入を確保する方法は多様です。
- 在宅ワーク(事務・ライティング・デザインなど)
- 週3〜4日の短時間勤務
- 職場まで30分以内の近距離勤務
これらは通勤負担を減らし、子どもとの時間を確保しやすくなります。
3. 精神面の充実を意識する
家庭優先の働き方は、社会的な接点が減ることで孤独感や不安を感じることがあります。
また、フルタイム勤務の正社員と比べられて格差を感じたり、場合によっては「下に扱われている」「バカにされている」と思ってしまうこともあるでしょう。
「その分の仕事量だから、それでOK」と割り切れるなら良いのですが、自分のキャリアにプライドを持ちすぎると、かえって苦しくなってしまうかもしれません。
だからこそ、家庭を優先する場合でも精神面の充実を意識することが大切です。
地域の子育てサークル、オンラインコミュニティ、趣味の集まりなど、外とのつながりを持ち続けることで、自分の存在意義や安心感を保つことができます。
4. 将来の方向転換も視野に入れる
「今は家庭優先」でも、数年後にキャリアを再構築する道はあります。
資格取得やスキルアップのための学びを少しずつ続けておくと、将来の選択肢が広がります。
家庭優先の働き方は、「今しかない時間」を大切にできる一方、将来の収入やキャリア面での備えも必要です。
自分と家族の幸せを守るために、短期的な快適さと長期的な安定を両立させる視点を持ちましょう。
育休後、今の職場で家庭優先が難しいときの選択肢
育休後に復職したものの、「想像以上に家庭との両立が難しい」と感じることは珍しくありません。
業務量や勤務時間の制限、職場の理解度など、環境によっては家庭優先の働き方が成立しない場合もあります。
そんな時、他部署へ異動願いを出せる規模の会社であれば良いですが、それが難しい場合は今の職場に固執せず、選択肢を広げて考えてみましょう。
部署異動や勤務形態の変更を交渉する
まずは現職での調整を試みます。
部署異動で業務内容や負担が軽減されるケースは少なくありません。
また、フルタイムから時短勤務への変更や、週数日のリモートワークを導入できないかを上司や人事に相談してみましょう。
このとき大切なのは、「子どものためだから仕方ない」という受け身の姿勢ではなく、「業務への影響を最小限にしながら成果を出す方法」をセットで提案することです。
契約社員・派遣社員への切り替え
正社員にこだわらず、雇用形態を変えることで働き方の自由度が高まる場合があります。
契約社員や派遣社員は勤務時間や期間が明確なことが多く、繁忙期や残業のコントロールがしやすいのが特徴です。
デメリットとしては、契約更新の不安定さや福利厚生の差がありますが、「今の生活に合う働き方」を優先するなら有効な選択肢です。
働く場所を変える(転職)
どうしても現職で条件が整わない場合は、転職を視野に入れましょう。
最近は「子育て世代歓迎」や「完全リモート可」の求人も増えています。
ただし、転職活動には時間と労力が必要なため、子どもや家庭の状況を踏まえてタイミングを計ることが重要です。
完全在宅ワークへの転向
パソコンや通信環境さえあれば、在宅でできる仕事は増えています。
事務作業やライティング、オンライン講師、カスタマーサポートなど、スキルや経験を活かせる仕事も多いです。
ただし、自宅での勤務は自己管理が必須。仕事と家事の境界があいまいにならないよう、時間割や作業スペースを決めておくことが成功のポイントです。
家庭優先が難しい環境でも、選択肢は必ずあります。大事なのは、「我慢する」か「辞める」かの二択ではなく、その間にある多様な道を見つけることです。
育休後の働き方は「自分がどう生きたいか」がすべての出発点
育休後の働き方に正解はありません。
キャリアを優先しても、家庭を優先しても、またその両立を目指しても、どれも立派な選択です。大切なのは、それが「自分で選んだ道」であること。
人は環境や周囲の意見に影響されやすく、「みんなそうしているから」「夫や家族に言われたから」という理由で働き方を決めてしまうことがあります。けれど、その選択が自分の価値観や理想から離れていると、時間が経つほどに違和感や不満が積み重なります。
だからこそ、出発点はいつも「自分がどう生きたいか」です。
自分の希望や優先順位を明確にすることで、たとえ環境が変わっても軸を保ちやすくなります。
もちろん、価値観や状況は時間とともに変わります。
子どもが成長したり、家庭の事情が変わったりすれば、働き方も見直す必要が出てくるでしょう。
そのときに「前にこう決めたから」と固くなりすぎる必要はありません。
育休後は、人生の中でも大きな転換期です。だからこそ、今の自分の心の声に耳を傾けることが、これからの数年間を心地よく過ごすための第一歩になります。そして、その積み重ねが、自分らしい生き方そのものを形作っていくのです。